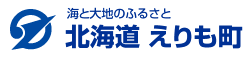国民健康保険
ページ内目次
国民健康保険とは
日本では、病気や事故にあったときの高額な医療費の負担を軽減するため、原則的にすべての国民がいずれかの医療保険に加入しなければなりません。
これを「国民皆保険制度」といいます。
職場の健康保険や共済組合に加入しているかたや生活保護を受けているかたを除いて、えりも町に住所のある75歳未満のかたは国民健康保険(国保)の加入者となります。
これを「国民皆保険制度」といいます。
職場の健康保険や共済組合に加入しているかたや生活保護を受けているかたを除いて、えりも町に住所のある75歳未満のかたは国民健康保険(国保)の加入者となります。
加入・脱退・変更などの各種届出
国保の加入・脱退・変更などの各種手続きは、世帯主の方が、事実が発生した日から14日以内に保健福祉課医療給付係(窓口3番)へ届け出をしていただきます。
国民健康保険に関する各種届出には、共通して次のものが必要です。
共通書類
国民健康保険に関する各種届出には、共通して次のものが必要です。
共通書類
- 世帯主および異動対象者の個人番号確認書類
世帯主と異動対象者(国保に加入するかた、脱退するかた、その他の届け出が必要なかた)の個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票など - 窓口で手続きするかたの本人確認書類
個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きのものなら1点
資格確認書、年金手帳など顔写真の無いものなら2点必要です。
上記に加えて必要な書類は手続きごとに異なりますので、下記の表をご確認ください。
加入するとき
| 届け出の内容 | 必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村から転入したとき |
|
| 職場の健康保険を脱退または扶養からはずれたとき |
|
| 健康保険の任意継続が終了したとき |
|
| 子どもが生まれたとき |
|
| 生活保護を受けなくなったとき |
|
脱退するとき
| 届け出の内容 | 必要なもの |
|---|---|
| 転出するとき |
|
| 職場の健康保険に加入または扶養されたとき |
|
| 生活保護が開始されたとき |
|
| 死亡したとき |
|
その他の届け出
| 届け出の内容 | 必要なもの |
|---|---|
| 資格確認書または資格情報のお知らせの記載事項に変更があったとき(住所、氏名、世帯主など) |
|
| 修学または施設入所のため他市町村へ移るとき |
|
| 資格確認書または資格情報のお知らせを破損、紛失したとき(再発行) |
|
マイナ保険証を利用されている場合も届け出が必要です
健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用しているかたは、加入、脱退時に新しい保険者での手続きが完了次第、資格確認書または資格情報のお知らせの発行を待たずにマイナ保険証で医療機関等を受診することができますが、届け出は引き続き必要となりますので忘れずに届け出してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和6年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ
改正マイナンバー法の施行により、令和6年12月2日以降、現行の国民健康保険被保険者証は新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)による資格確認を基本とする仕組みに移行されています。
なお、マイナンバーカードをお持ちでないかたや、健康保険証の利用登録をされていないかたには、有効期限が経過する前にえりも町から「資格確認書」が交付されますので、保険証が発行されなくなったあとも引き続き保険医療を受けられます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
なお、マイナンバーカードをお持ちでないかたや、健康保険証の利用登録をされていないかたには、有効期限が経過する前にえりも町から「資格確認書」が交付されますので、保険証が発行されなくなったあとも引き続き保険医療を受けられます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
医療機関等での一部負担金
マイナ保険証または資格確認書を医療機関の窓口で提示することにより、かかった医療費の一部を負担することで診療が受けられます。
残りの医療費は国民健康保険が負担します。
残りの医療費は国民健康保険が負担します。
0歳から69歳までのかたの一部負担金の割合
| 区分 | 負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前 (6歳到達後最初の3月31日まで |
2割 |
| 義務教育就学年齢以上から69歳以下 | 3割 |
70歳から74歳までのかたの一部負担金の割合
70歳になると誕生日の属する月の翌月(1日生まれのかたは当月)から高齢受給者に切り替わります。
マイナ保険証未保有者のかたには切り替え月の前月中に新しい資格確認書をご自宅へ簡易書留にて、マイナ保険証をお持ちのかたには切り替え月の前月中に新しい資格情報のお知らせを普通郵便にて送付いたしますので、ご自身で翌月1日に差し替えをお願いします。
マイナ保険証未保有者のかたには切り替え月の前月中に新しい資格確認書をご自宅へ簡易書留にて、マイナ保険証をお持ちのかたには切り替え月の前月中に新しい資格情報のお知らせを普通郵便にて送付いたしますので、ご自身で翌月1日に差し替えをお願いします。
| 住民税の課税所得金額 | 負担割合 |
|---|---|
| 同一世帯の70歳以上の国保の加入者の 課税所得金額が全員145万円未満 |
2割 |
| 同一世帯の70歳以上の国保の加入者のうち もっとも高いかたの課税所得金額が145万円以上 |
3割 |
- 同一世帯の70歳以上の国保の加入者の基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下の場合も2割となります。
基準収入額適用申請
上記で負担割合が3割と判定されたかたのうち、収入が以下の基準に該当するかたは申請をすることで2割負担となります。
同一世帯の70歳から74歳の国保の被保険者の収入合計額
同一世帯の70歳から74歳の国保の被保険者の収入合計額
- 単身世帯の場合、383万円未満
- 複数いる世帯の場合、520万円未満(旧国保被保険者がいる場合も含みます)
その他受けられる給付
病気やけがなどで医療費が高額になったとき、治療用装具を作ったとき、出産や死亡があったときなど、国保では次のような給付をおこなっています。
高額療養費/限度額適用認定証
入院や手術などで医療費が高額となった場合、支給要件を満たしていれば高額療養費の支給申請をすることができます。
また、限度額適用認定を受けることで、医療機関等の窓口で自己負担を限度額まででおさえることもできます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
また、限度額適用認定を受けることで、医療機関等の窓口で自己負担を限度額まででおさえることもできます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
療養費・海外療養費・移送費
やむを得ずマイナ保険証や資格確認書をを持たずに治療を受け10割負担となったときやコルセットなどの治療用装具を作ったとき、海外渡航中に治療を受けたとき、医師の指示による移送を行なった場合などは、いったん自己負担となりますが、申請をすることで一部負担金以外の額が国保から支給されます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
出産育児一時金
国保の被保険者が出産したときに支給されます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
葬祭費
国保の被保険者がお亡くなりになったとき、葬祭を行なったかたに対してえりも町より葬祭費として30,000円が支給されます。
支給は申請によりおこないますので、該当する場合は次の書類をご持参のうえお手続きにお越しください。
支給は申請によりおこないますので、該当する場合は次の書類をご持参のうえお手続きにお越しください。
- 会葬礼状や新聞広告、領収書など、葬祭日、葬祭を行なったかたを確認できるもの
- 葬祭を行なったかたの名義の振込先確認書類
- 葬祭を行なったかたのマイナンバーカード
- お亡くなりになったかたの資格確認書(お持ちの場合のみ)
交通事故などで医療機関を受診する場合
交通事故など、第三者の過失によって傷病を受けた場合で国保を使って治療を受ける場合、「第三者行為による傷病届」が必要です。
この届出がないと国保が使えない場合がありますので、交通事故があったらすぐに警察に届けるとともに国保担当窓口への届出も忘れずにしましょう。
この届出がないと国保が使えない場合がありますので、交通事故があったらすぐに警察に届けるとともに国保担当窓口への届出も忘れずにしましょう。
国民健康保険証の有効期限及び更新
令和6年12月1日までに交付した保険証の有効期限は令和7年7月31日までとなっています。
令和7年8月1日からお使いいただく保険証等は、マイナ保険証の保有状況により種類が異なります。
令和7年8月1日からお使いいただく保険証等は、マイナ保険証の保有状況により種類が異なります。
マイナ保険証をお持ちのかた
マイナンバーカードの保険証利用登録をしているかた
資格情報のお知らせを交付します。受診の際はマイナンバーカードを提示してください。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証による受付が未対応の医療機関や、何らかの事情で医療機関などの窓口でマイナ保険証による受付がうまくいかなかったときに、マイナンバーカードをともに提示することでスムーズに受診することができます。
「資格情報のお知らせ」の右下部分のカード(薄紫色の部分)を切り取ってマイナンバーカードと一緒に保管してください。
なお、マイナ保険証をお持ちの場合でも、介助者などの第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がいのあるかたなどの要配慮者は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証による受付が未対応の医療機関や、何らかの事情で医療機関などの窓口でマイナ保険証による受付がうまくいかなかったときに、マイナンバーカードをともに提示することでスムーズに受診することができます。
「資格情報のお知らせ」の右下部分のカード(薄紫色の部分)を切り取ってマイナンバーカードと一緒に保管してください。
なお、マイナ保険証をお持ちの場合でも、介助者などの第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がいのあるかたなどの要配慮者は、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちでないかた
マイナンバーカードの保険証利用登録をしていないかた・マイナンバーカードをお持ちでないかた
資格確認書を交付します。受診の際は資格確認書を提示してください。
「資格確認書」は、マイナ保険証をお持ちでないかたに、従来の保険証の代替として交付します。
従来の保険証と同様に医療機関窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。
7月中旬以降、順次、簡易書留でご自宅に郵送しておりますので、お持ちの保険証と差し替えてください。
「資格確認書」は、マイナ保険証をお持ちでないかたに、従来の保険証の代替として交付します。
従来の保険証と同様に医療機関窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。
7月中旬以降、順次、簡易書留でご自宅に郵送しておりますので、お持ちの保険証と差し替えてください。
DV・虐待等被害者への資格確認書の交付等について
DV・虐待等被害者への資格確認書の交付等については下記のページをご覧ください。
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 医療給付係
- 電話番号:01466-2-4622
- ファクシミリ:01466-2-4632
- お問い合わせフォーム